
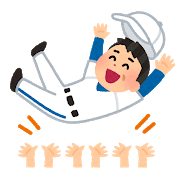
新人チームになって早2か月が経とうとしています。この度(9月18日<土>に)開催された「両沼支部新人大会」において、本校野球部が見事優勝しました。おめでとうございました。新鶴中に3対2で勝利し、決勝は湯川中と対戦し9対0で快勝しました。今後は、10月2日(土)・3日(日)に開催される会津大会に進出します。応援をよろしくお願いします。
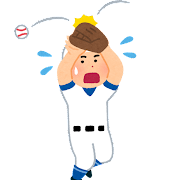

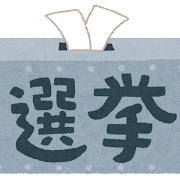

9月17日(金)は生徒会役員の改選でした。本来なら一人一人の演説の後、全校生による投票を行い、即日開票となるわけですが、2年連続すべての役職において定数と立候補者が同数ということで無投票での当選確定となりました。おめでとうございます。いよいよ3年生から1・2年生へのバトンタッチです。新役員の皆さん、今までの伝統のうえにまた新たな高田中の伝統を築いていってほしいと思います。
会 長:熊倉 瑠香さん(2年)
副 会 長:三星 優奈さん(2年)
執行部員:横山 裕貴くん(2年)
〃 :齋藤 和瑛くん(2年)
〃 :大橋 晴さん(1年)
〃 :増井 智理くん(1年)






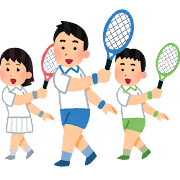
9月11日(土)・12日(日)に、あいづ総合運動公園テニスコートにおいて「秋季全会津中学生ソフトテニス大会」が開催されました。新人チームとして、公式戦を戦ってきました。試合結果は以下のとおりです。なお、県大会は11月6日(土)・7日(日)に福島市(福島吾妻テニス競技場)で行われます。応援よろしくお願いいたします。
【個人】星見 天海・鈴木 健心ペア(ベスト 8)県大会出場
長嶺 悠樹・羽賀 礼稀ペア(ベスト16)県大会出場
【団体】女子団体選手権の部(ベスト8)Sリーグへ進出
女子団体研修の部(ベスト8)
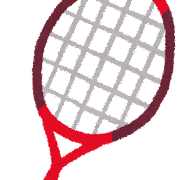
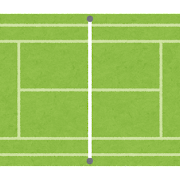






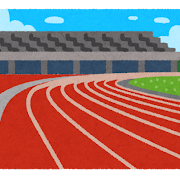

先週末は、あいづ陸上競技場において「令和3年度福島県中学校新人陸上競技大会会津地区予選会」が行われました。本校からも多くの1・2年生が参加し活躍してきました。
県大会は10月9日(土)~10日(日)に、郡山ヒロセ開成山陸上競技場で行われます。県大会への出場権を得た皆さんは頑張ってきてください!8位までの入賞者は以下のとおりです。お疲れさまでした。
【男子】(県大会は1人1種目)
・中学共通男子800m 優 勝 渡部 勇輝くん
・中学2年男子走幅跳 第2位 北条奏一郎くん(県大会進出)
・中学共通男子3000m 第3位 渡部 勇輝くん(県大会出場)
・中学1年男子走幅跳 第3位 熊田 幸延くん
・中学1年男子100m 第5位 熊田 幸延くん(県大会出場)
・中学共通男子800m 第6位 吉田進次朗くん(県大会出場)
・中学共通男子800m 第8位 鈴木 啓介くん
【女子】(県大会は1人1種目)
・中学1年女子100mH 第2位 大橋 晴さん(県大会出場)
・中学2年女子100m 第4位 千葉来琉未さん(県大会出場)
・中学共通女子200m 第4位 千葉来琉未さん
・中学2年女子1500m 第4位 児島 綺羽さん(県大会出場)
・中学2年女子走幅跳 第4位 岩田 心遥さん(県大会出場)
・中学共通女子4×100mR第6位 高田中チーム
・中学2年女子1500m 第7位 馬場あかねさん
・中学2年女子100mH 第7位 長嶺 里奈さん

