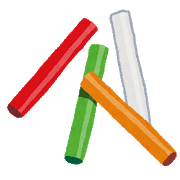

今週、7月5日(月)~7日(水)までの3日間は、郡山開成山陸上競技場において令和3年度の福島県中体連陸上競技大会が開催されました。本校からは16名の生徒の皆さんが出場し大活躍でした。正式な大会としては2年ぶりの開催となり、県大会が開催されるだけでもありがたい限りです。選手の皆さん、立派な大会参加の姿勢でしたよ。カッコよかった!
みんなが大活躍でしたが、その中で主な成績を紹介します。
・男子共通3000m 優 勝 吉田遼太朗くん(東北大会・全国大会出場権獲得)
・男子共通1500m 第4位 猪股 秀哉くん(東北大会出場権獲得)
・女子低学年リレー 第4位 大橋 晴さん 千葉来琉未さん
渡部 月輝さん 長嶺 紅葉さん
(東北大会出場権獲得)
・男子共通800m 第6位 秋山 勇人くん
・女子走り高跳び 第7位 野中 瑠愛さん
・男子1年1500m 第10位 吉田進次朗くん


なお今後、東北大会は8月8日(日)~9日(月):秋田県「県営陸上競技場」において、全国大会は8月17日(火)~20日(金):茨城県「笠松運動公園陸上競技場」においてそれぞれ行われます。がんばれ陸上部!がんばれ高中生!




【7月5日(月)~7月10日(金)】
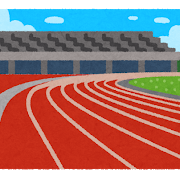

7月5日(月)ALT来校
県中体連陸上大会1日目(郡山開成山陸上競技場)
下校スクールバス(第1便)16:30
下校スクールバス(第2便)18:00
日番:星佳子先生
7月6日(火)ALT来校
県中体連陸上大会2日目(郡山開成山陸上競技場)
ICT支援員来校
下校スクールバス(第1便)16:30
下校スクールバス(第2便)18:00
日番:松本孝先生
7月7日(水)ノー部活デイ
県中体連陸上大会3日目(郡山開成山陸上競技場)
フッ化物洗口
高校説明会 3学年スクエア
下校スクールバス16:30(1便のみ)
日番:小林先生
7月8日(木)
下校スクールバス(第1便)16:30
下校スクールバス(第2便)18:00
日番:星佳子先生
7月9日(金)ALT来校
漢字コンテスト
全校集会
御田植え祭事前指導
下校スクールバス(第1便)16:30
下校スクールバス(第2便)18:00
日番:松本孝先生
7月10日(土)2学年「立志式」3・4校時10:40~
1学期末保護者会14:00~15:00
弁当持参!(給食なし)
下校スクールバス13:40(1便のみ)
日番:小林先生

